前回まで、PDCAの目的、目標について書いて来ました。
今回はPLAN(計画)の立て方について書いていこうと思います。
先に簡単な手順を記します。
①目標(期日、定量化、イメージの3点セット)を決める
②目標と現状のGapを言語化する
③Gapが生じている問題を書き出す
④取り組む問題を3つ以内に仕分け(問題から課題へ)
⑤課題解決の進捗を見える化する(KPIを決める)
⑥KPIを達成する解決案(方向性)を書き出す
⑦具体的解決策を優先順位付けする
それでは具体例を使って説明したいと思います。
製造業で長年勤務してきたので、工場のモノづくり現場を例にしますが、PDCAは何でも対象にすることが出来ます。対象によって少し要領は変わりますが、基本は同じです。
以下の実例は、一人で行ったのではなく、会議や打ち合わせの中で進めた事項です。
①目標:
3か月後に製品Zの不良率を3%以下にする
(既存製品の平均不良率は1%以下ですが、いきなり1%以下を目指すのは無理という事で半分以下を目標にしました)
②目標と現状のGap:
現在月平均の不良率が6%台なので半分以下にしなければいけない
③Gapが生じている問題事項:
以下はブレーンストーミング的に会議をした中で出てきた意見を箇条書きにしたモノです。こういう時は、意見の粒感も大きかったり、小さかったりしますが、出た意見を否定せず、ただひたすらホワイトボードに書いていきました。中には不満、苦情的なモノも含まれますが、同意するのでは無く、受け止めるようにします。
・不良は「打こん」と「キズ」が多いと聞いているが、発生状況が分からない
・発生工程が分からない
・量産移管されたばかりで、製造条件が安定していない
・現場の担当者も作業手順が十分に教育されていない
・注文のロットの大きさもマチマチで、突発的に特急要請があって困る
・設備が古いタイプで調整に時間も掛かるし、扱える人が限られる
・原料の保管期限が守られていない(原料は客先から供給のため)
・メインの製品の生産が繁忙で残業も増えて、オーバーワークになっている
・ベテランが辞めて金型段取りの品質レベルが落ちている
・今は忙しくて、納期対応だけで一杯一杯で時間が無い
10名前後の参加者でしたが、さまざまな意見を出してもらいます。
④課題化(取り組む問題を3つ以内に仕分け/優先順位をつける):
すべてを解決出来ればいいのですが、現実は人も時間も限られます。ましてや、人は新たに仕事が増やすことを好みません。ブレストで出た意見の粒感をそろえたり、一言でまとめたりしながら、課題として取り組む事項を仕分けします。以下の3つにまとめました。
■現状把握が出来ていない
■作業手順など基本ルールが守られていない
■技能レベルが担当者ごとにバラついている
仕分けをする時のコツは、ブレストで出た問題事項を、仕分けする基準を持つことです。例えば、(1)重要だと思うもの3つ、(2)緊急性のあるもの3つ、(3)簡単に取り組めるもの3つ、(4)やりたいと思うもの3つ・・・というように〇△◇☆で囲っていきます。たくさん重なった事項3つを選択したり、会議の中で、色違いの付箋を配って、ホワイトボードに投票したりします。
実際にPLANを立てたあとにDOで、行動する人が納得して取り組めるようにする事が大切です。
⑤課題のKPI化
KPIというと難しく聞こえるかも知れませんが、Key Performance Indicatorの略です。課題の達成状況を数値で判断できるようにするためです。このKPIで考え過ぎて、混乱してしまうパターンは多いです。
また、初めての取組みなど、やってみないと分からない目標の場合、どうしても抽象的であったり、定性的な表現になってしまいますが、仕方ありません。最初はみんな、そんなもんです。
どうしても難しい時や、PDCAに慣れていない時は、考え過ぎず、仮決めして進めてはどうでしょうか。KPIで混乱して、前に進まないよりは、まずは前に進めることを優先するのがコツです。やってみて、違和感があれば、修正すればいいですから。
また、KPIはいくつも考えが出てくると思います。「正解を見つけないと」と考え込む方もみえます。正解はありませんから、良いと思うものを1つ決めて、気軽にやってみましょう。
■現状把握が出来ていない:最重要KPI
KPI:定例品質会議1回/週から3回/週(月水金)に増やし、調査結果を見える化する
■作業手順など基本ルールが守られていない:
KPI:各工程ごとに失敗事例(状況→行動→結果)を記録/共有し、1回/月読み合わせ
■技能レベルが担当者ごとにバラついている
KPI:スキルマップを活用した技能講習会を1回/月で継続する
以上列挙したKPIですが、「最重要KPI」を一つ決めておくといいです。ここを管理、コントロールできればGoal(目標)達成に大きく近づけるというモノを決めて下さい。
⑥KPIを達成する解決案(方向性)を書き出す
■現状把握が出来ていない:最重要KPI
・各工程ごとに全数目視検査実施して不良種別ごとに集計する
・不良観察所見を6W3Hと5M2Eで情報を整理する
・発生率の高い不良3つに絞り、発生工程/箇所、発生時間帯を特定する
・上記情報を共有したうえで、発生原因の仮説を立案する
■作業手順など基本ルールが守られていない
・手順の内容、表現、表示が分かりやすさの確認修正
(手順書など何年も更新されずに放置されていないか?)
・守れるルールになっているか? 守るために修正する箇所は無いか? 協議する
・どんな状況で、どんな行動を取ったら、どんな結果になったか?を考えまとめる
(原因分析を人に当てるのでは無く、行動にフォーカスする)
■技能レベルが担当者ごとにバラついている
・スキルマップ表のメンテナンス
・技能保有者と講習会実施に向けた打ち合わせ
・担当者と技能レベルアップを目的に月例の面談をする
⑦具体的解決策を絞り込む
これまで同様にブレーンストーミングで出たアイデア、解決策を優先順位付けします。仕分けの軸は、重要度、緊急度、実行容易度、やりたい度・・・etc.で考えたりします。重要KPIは当然優先順位は高くなります。
以上、①~⑦までの流れは、目標を達成するための行動を、どんどん細分化/数値化しながら、実行可能な小さな行動にしていく作業です。目標が大きなままだと、行動に移せないという事です。そして、すべては実行できませんので、優先順位を付けて、やる事を絞ることです。
■ 目標達成に向けた行動を細分化して、実行可能な小さな行動にする
■ 優先順位を付けて、やる事は3つ以内(1つでも全然OK)
ここまでまとめたモノは、ガンチャートのような工程表にまとめ、見易さや進捗確認するための工夫を施せば完成です。そこまで行かなくても、目標を明確にして、細分化して行動に移すところまで、一度やってみてはどうでしょうか?
それでは、次回はD(実行・実績)について書いてみます。
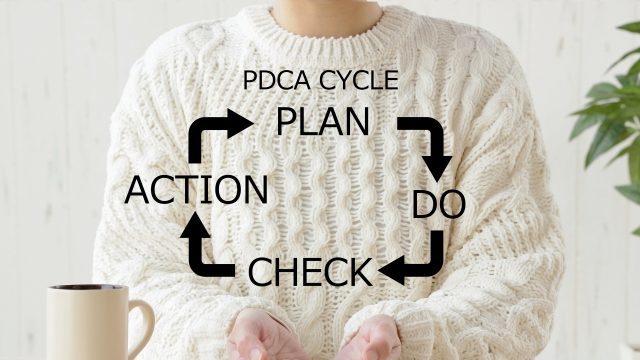

コメント